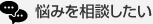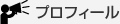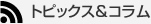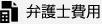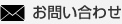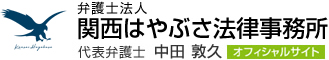弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

破産・免責手続について
破産宣告とは
破産とは、一般的に、債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産開始決定を受ける手続のことを言います。
申し立てを行うのは、基本的に債務者である個人や法人であり、弁護士がその申立代理人となって、破産申立手続を行う場合が多いでしょう。申立は、破産申立書を裁判所に提出して行います。
破産申立を行うにあたって問題となるのは、同時破産廃止の手続の申立を出来るかどうかという点です。同時破産廃止とは、債務者の財産がほとんどなく、わざわざ破産管財人を選任して、資産をお金に換えて、債権者に配当する手続きを践む必要がなく、かえってこのような破産手続を進める費用すら出ない場合に、裁判所が、破産開始決定を行うと同時に、破産手続を終結させる趣旨で下す決定のことです。
破産の申立がなされると裁判所は、申立書を審査し、その上で債務者を裁判所に呼びだして、審尋(面談)を行います。但し最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合がほとんどになったようです。
以上の結果、債務者に破産原因があると認めた場合には、破産(手続)開始決定を下します。債務者に一定以上の資産がある場合には、破産管財人が選任され、その資産をお金に換え、債権者に配当する手続を開始します。資産がなく、破産管財人が選任されない場合には、同時破産廃止決定を下します。
免責決定とは
破産を申し立てたのが個人である場合、破産宣告を受けただけでは、債務の支払いを免れることが出来ません。破産手続の後行われる免責手続において免責決定をもらう必要があります。免責手続は、破産手続に引き続いてなされますが、一応破産手続とは別の手続で、破産者が債権者に対する債務の支払いから免れるための手続です。
免責申立がなされると裁判所は、(再び)破産者を裁判所に呼び出して、審尋(面談)を行います。但し最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合がほとんどになったようです。場合によっては、集団免責審尋(破産者が多数同室に集められ、壇上で裁判官が免責について説明したり、破産者に質問したりする審尋方式)という審尋が行われるケースもあります。
ここで注意しなければならないのは、破産者の負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルであったりする等破産者に一定の不誠実な事由(免責不許可事由)がある場合には、裁判所は、免責の不許可決定を下す可能性が高いということです。
但し、大阪地裁においては、免責観察型の管財事件も行っているようで、ある程度重大な免責不許可事由が認められる破産者に破産管財人を付け、すなわち破産管財事件として、破産管財人が破産者の家計管理状況等を一定期間観察指導したり、例えば破産者にいくらかの金銭の積立を指示し、破産者がそれを誠実に行えば、破産管財人の意見を聞き、裁判所が免責決定を下すという運用も行っているようです。ですから、免責不許可決定が確定してしまう破産者というのは、よほど不誠実な破産者であるということができるでしょう。
免責手続において、破産者に一応免責不許可事由がみあたらない場合には、裁判所は、1ヶ月以上の期間を定めて、債権者から破産者の免責について異議を申し立てる機会を与えます。この裁判所が定めた異議申立期間内に、債権者から何らの異議が申し立てられなければ、裁判所は、破産者に対して、免責決定を下すことになります。
免責決定を得ると、破産者は、債権者らに対して負っていた債務の全部の支払いを免れることになります。但し、租税や、故意による損害賠償義務、破産者が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった債務等免責の効力が及ばず、支払いをしなければならない債務がありますので注意を要します。
雑感
確かに破産・免責という制度は、債権者からしてみると、借金を踏み倒されるわけですから、たまったものではないでしょう。しかし、やむを得ずに出来た過大な借金の返済から債務者を解放し、人生の再スタートを切る手助けをするという意味では、実に近代的な制度であり、近代社会では不可欠の制度といえます。ただ、破産制度により保護されるのは、あくまでも誠実な債務者であり、ギャンブラーや浪費者等不誠実な債務者は保護されない場合があることは当然でしょう。
弁護士費用
破産(免責)申立を行う場合の弁護士費用についてですが、同時廃止となる事案については、原則として着手金として21万円(消費税込・費用別)(債権者が15件までの場合)となっております。
但し、事案が複雑な案件、債権者が15件を超える場合や、負債総額が額面上1000万円以上ある場合には、あなたと協議の上、1万円から4万円程度着手金を加算させて頂きます。破産管財事件となる事案についての着手金につきましては、個人の方の場合で、その財産規模や営業規模、債権者数、負債総額により、あなたと協議の上、20万円から30万円(消費税・費用別)の範囲で決定させていただきます。
さらに破産管財事件の場合、裁判所に納める予納金(破産管財人に引き渡す費用)として別途20万5000円から50万円程度(以上の場合あり)の費用が必要となってきます。法人の破産申立に関する弁護士費用につきましては、法律相談をお受けした上、代表者様と協議の上決定させていただきます。
なお、分割払いについてですが、弁護士費用は一括払いが原則ですが、それが困難な方の場合、最初に着手金額の一部(5万円から10万円程度)をお支払い頂き、残りを毎月4万円から5万円程度の分割払いでお支払い頂くことは可能です。
なお申立準備のための依頼者との打ち合わせ、申立後の裁判所に対する対応は、事務員任せではなく基本的にすべて弁護士自身が対応いたしますのでご安心ください。
破産(免責)申立についての報酬金は頂いておりません。
任意整理(債務整理)・過払金返還について
任意整理(債務整理)とは
任意整理(債務整理)とは、債務者(代理人弁護士)が、裁判所の手続を利用するのではなく、債権者らと個別に交渉し、債務の弁済についての和解を行っていくものです。
これを行うメリットは、たとえば勤務先の会社からの借入については何の問題もなく返済が出来ているが、サラ金からの借入については、利息が高く、返済するのに無理が出てきたので、サラ金何件か分の債務についてだけ、月々の返済金額を下げてもらいたい、といった場合や、住宅ローンを抱えていて、これについては、これ以上の長期間の分割弁済の交渉の余地もないが、サラ金・信販関係の借入についてだけ、やはり月々の返済額が楽になるように交渉したいという場合などに、支払いが困難になってきた借入についてだけとりあげて、長期分割弁済の方向で話し合いをしたり出来る点です。
任意整理のデメリットとしては、あくまでも債権者と債務者(代理人弁護士)との任意の交渉であるため、条件が折り合わなければ、いつまでたっても話し合いがつかないというケースも出てきます。
また、債権者が債務者との取引履歴(貸付と返済の履歴)をすべて開示してくれなければ、話し合いが進まなかったりします。
さらに、任意整理は、裁判所の手続ではなく強制力がないので、利息を利息制限法に沿った利率で、取引の初めの分から計算し直してもらうことは出来ても、元本のカットまでは、原則的に応じてもらえません(但し、一括でまとまった金額を支払うので残りを免除してということであれば、交渉の余地はありますが・・・)。
以上のメリットやデメリットを踏まえた上で、任意整理を行う場合、債務者本人が債権者と交渉するにはやはり無理があります。弁護士に交渉を依頼しなければ、債権者もなかなか話し合いに応じてくれないことが多いので、弁護士に交渉を依頼したほうがよいでしょう。以下、債権者がサラ金業者や信販会社である場合を念頭において、交渉の流れを解説します。
弁護士が、債務者から任意整理の依頼を受けた場合、債権者らに受任通知や債権届出書を送付し、債権者らの債権額を調査します。もちろん、債権者には、債務者との取引開始時点からのすべての取引履歴(貸付と返済の履歴)を開示してもらい、利息制限法所定の利率で計算し直した場合の残債務額も提出してもらうことになります(もっとも最近では、取引履歴は開示しても、利息制限法所定の利率での再計算は、勝手に弁護士がやれという姿勢の債権者らが多くなりました。)。
一般的に当該債権者との取引が長ければ長いほど、利息制限法所定の利率で計算し直してみると、残債務額は実ははるかに安かったという結果になることが多いです。
このようにして債権者らの正確な債権額を調査したうえで、さらに弁護士は、その残債務額を金額固定してもらった上で、すなわち将来の利息が発生しないようにしてもらった上で、その固定された金額を、3年間~5年間の分割弁済にしてくれるように債権者と交渉を行います。分割弁済の期間が5年間を超えてくると、債権者も交渉に応じてくれないことが多いようです。
返済金額を固定した上で、これを3年間~5年間の分割弁済にしてもらえれば、たいていの債務者の返済の負担は、格段に楽になります。少なくとも、利息ばかりを支払って、元本がいっこうに減らないといったことはなくなるでしょう。
このように固定された金額を、長期分割にしてくれるという話が債権者との間でまとまれば、あとは和解契約書を債権者との間で締結します。任意整理の対象としたすべての債権者との間で和解契約書が締結できれば、任意整理は終了します。
なお、和解が成立した以上、和解契約書に定められたとおりに、債務者ご自身が責任を持って分割金を支払っていかなければならないことはもちろんです。
※以上は、個人の方の任意整理(債務整理)について説明したものです。法人の債務整理にはあてはまりません。
過払金(過払い金)の返還請求について
債務者の取引開始時点からのすべての取引履歴(貸付と返済の履歴)を開示してもらい、利息制限法所定の利率で計算し直した場合の残債務額がマイナスになる場合、債務者は、利息制限法上の利息計算によれば、お金を返済しすぎていることになります。
すなわち、今まで利息と思って支払っていた分が元本に充当されるため、元本がどんどん減っていって完済し、その後さらに支払ったために払いすぎになるのです。
このような返済しすぎのお金を過払い金(過払金)と言います。一般的に5年以上同じサラ金で借りたり返したりを繰り返していると、すでに負債は完済し、過払いになっているケースが多いといえます。
が、最近大金を借りたなどの事情があったり、返済をあまりしていなかった等の事情によっては過払いになっておらず、負債が残っているケースもあります。
仮に、利息制限法による再計算の結果、過払い金が発生している場合、その分は債権者が債務者のお金を不当に利得していることになりますから、当然そのお金の返還及びこれに対する年5パーセントの利息金を逆に請求することになります。
ただし、話し合いにより速やかに返還してもらおうとする場合、債権者から過払い金元本の8割とか9割の返還ならすぐにでも応じるが、それ以上返還せよと言うなら訴訟をしてくれと言われる場合が多いです。
このような場合は依頼者の意見を聞いた上で、過払い金元本の8,9割程度の返還で和解に応じるか、元本10割の返還及び利息金の支払いを求めて訴訟を提起するかを選択することになります。訴訟をするということになれば、よけいに費用や時間がかかりますから、元本の8,9割程度の返還で和解するケースの方が多いように思います。
弁護士費用
個人の方が任意整理を行う場合の弁護士費用についてですが、着手金・費用として、借入先1件あたり2万2000円(諸費用・消費税込み)となっています。報酬金については、次の額のいずれか多い方の金額によります。
(1)業者の請求額を減額させた減額額の10%+過払い金が存する場合は、業者から過払返還を受けた金額の15%の金額(消費税別)
(2)業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で、2年以上の長期分割弁済とした場合、分割総額の5%の金額(消費税別)
なお債権者らとの交渉は、事務員任せではなく基本的にすべて弁護士自身が対応いたしますのでご安心ください。
尋問の実際の風景
よく日本のテレビドラマや邦画で、法廷で弁護士などが尋問を行っているシーンがあったりします(外国の裁判のことはよく分かりませんので、洋画や外国ドラマは除きます)。
しかし、ドラマや映画で役者がやっている尋問風のもの、アレは尋問ではありません。もうほとんど謎解き独り言、あるいは演説と言っていい類のもので、尋問の体をなしていないのがほとんどです。実際の尋問は以下のようなものです。
法廷での尋問は(民事事件を前提にすると)、原告や被告や第三者つまり証人に証言して貰い、事実関係を聞き出す手続です。そうです、聞き出すのはあくまでも「事実」です。「意見」でもないし「評価」でもありません。「過去に起こった事実」を聞き出す手続です。
そして、しゃべるのは、ほとんど、原告本人や、被告本人や証人でなければならず、原告代理人か、被告代理人である弁護士、そして裁判官も、尋問においては常に質問し続ける立場なのです。質問せずにべらべら弁護士がしゃべったりすると、必ず裁判官から「あなた何しゃべってるの?質問してくださいよ!」と注意されてしまうでしょう。
例えば私が、被告代理人で、被告側で証言するのは被告本人だけ、原告側で証言するのは、原告本人と証人1人としましょう。
証言の順番は、①証人②原告本人③被告本人の順番になるのがセオリーでしょう。
この場合ですと、①証人に対して、原告代理人が主尋問、私が反対尋問、裁判官尋問②原告本人に対して、原告代理人が主尋問、私が反対尋問、裁判官尋問③被告本人に対して、私が主尋問、原告代理人が反対尋問、裁判官尋問という順番で尋問が行われていきます。
この場合、原告代理人は、自分側の証人や原告本人に対して、主尋問を行い、原告の主張に沿う証言をさせて、その立証を固めます。一方被告代理人の私は、証人や原告本人に対して反対尋問を行い、その証言の矛盾点を問いただして、原告の立証を崩さなければなりません。
被告本人に対しては、私が主尋問を行い、被告の主張に沿う証言をさせて、その立証を固めます。これに対して、原告代理人は、被告本人に反対尋問を行い、その証言の矛盾点を問いただして、被告の立証を崩しにかかります。
裁判官は、公平な観点から、聞かなければならないと思う点を、証人や原告や被告に対し、補充的に尋問します。
証人や原告や被告がしゃべる内容は、基本的に予め陳述書という書証を作成し、裁判所に証拠として提出してから尋問が行われます。つまり、尋問当日には、原告や被告や証人が何をしゃべるのか、大体誰もが分かっている状態で尋問に臨むのです。
各人の陳述書が予め出ているのですから、審理の短縮化のために、尋問時間は短くなっている傾向があります。
事案にもよりますが、例えば、裁判官から、証人や原告や被告の主尋問は各20分で、反対尋問も各20分で収めてくださいというような訴訟指揮がされる感じです。それでも、1人につき主尋問・反対尋問・裁判官の尋問で40分以上尋問を行うことになるので、3人の尋問を行えば、尋問時間はトータルで120分を優に超えます。
ですので、弁護士はのんびりとおしゃべりしている暇はありません。尋問事項のポイントを絞って、基本的に一問一答方式で尋問を進めなければ、とうてい予定の尋問時間で尋問を終えることなど出来ないのです。
証人や原告や被告には基本は「はい」か「いいえ」で答えて貰うのです。それでも足りない場合は、追加追加で一問一問を継ぎ足し、追加追加で一答一答を繰り返して貰うのです。
被告代理人の私としては、第一目標としては、被告本人の主尋問・反対尋問を無難に乗りきらなければなりません。つまり予め提出している陳述書とまるで違うような証言を被告本人がしないように、予め原告代理人の反対尋問も想定した上で、被告本人と打ち合わせしておかなければなりません。
また私としては、証人や原告本人に有効な反対尋問を行わなければなりません。有効な反対尋問とは、証人や原告本人が必ず、少なくとも高確率で、それまでの陳述と矛盾した答えになるか、答えに窮するような反対尋問でなければなりません。証人や原告本人がすらすらと説明できてしまうような反対尋問は、相手の立証の手伝いをしているだけですから、そんな反対尋問はしない方がましです。
ですので反対尋問は、よほど準備して臨まなければならないものであり、予めの準備段階で有効な反対尋問が思い浮かばないような場合は、尋問当日の証人や原告本人の証言の巧い下手を見極めて、しゃべるのが上手な証人や原告本人の場合は、早々に反対尋問を切り上げた方が良い場合もあります。一方、予め提出している陳述書とまるで違う証言をぽろぽろとしてしまう証人や原告本人の場合、臨機応変にこれらの証言の矛盾点に切り込んでいくような反対尋問をどんどんすべき場合もあります。
長くなりましたが、以上のような基本的に一問一答スタイルの尋問が、日本の法廷における尋問の実際の風景です。一般の方が見ていて面白いものとは言い難いのが現状でしょうね。ドラマじゃないんです。映画でもないんです。実際の尋問は。
内容証明郵便について
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、どのような内容の文書を郵送したか郵便局において証明してもらえる郵便物のことです。この内容証明郵便を、配達証明(内容証明郵便が受取人にいつ到達したかを証明してくれるハガキ、後日郵便局から差出人に送付してくれる)をつけてもらって郵送した場合、相手方におこなった意思表示の内容、時期を証明できるので、後日の証拠とすることができます。
内容証明郵便を利用すべき場合としては、次のような場合が考えられます。例えば借地契約の契約期間満了の際、借地人が契約の更新請求をしたのに地主が遅滞なく異議を述べないときは借地契約は更新したものとみなされますし、建物賃貸借契約において当事者が契約期間満了前の一定期間内に相手方に対して契約を更新しない旨の通知をしないと賃貸借契約は更新したものとみなされます。また、債権の譲渡があった場合に、これを第三者に対抗するためには、譲渡人が、確定日付(ある文書がその日に作成されたことが法律上証明される日付)付きで、債務者へ債権譲渡通知を行うか債務者が承諾を行わなければなりません。また、ある契約を相手方の債務不履行を理由に解除する場合にも契約解除の意思表示を明確に行う必要があります。
さらには、貸金債権などの債権等は一定期間権利行使をしないでいると消滅時効が完成してしまいますし、土地や建物の占有者は、一定期間これらの不動産を占有継続すると取得時効により所有権を取得してしまうということもあります。そのようなときには支払請求(明渡請求)を行うことで時効の中断を行う必要がありますが、かかる場合には後日の証拠とするために内容証明郵便を利用すべきなのです。
内容証明郵便の形式
内容証明郵便は、決まった文書の形式で出す必要があります。すなわち縦書きの場合、①1行20字(句読点も1字)以内、1枚26行以内で作成しなければなりません。横書きの場合には、②1行13字以内、1枚40行以内、あるいは③1行26字以内、1枚20行以内で作成することとになっています。文書が2枚以上の用紙にわたる場合にはその綴目に契印をします。なお、用紙については特に制限はなく、コピー用紙やワープロ用紙でも構いません。また内容証明郵便専用のマス目が印刷された用紙も市販されていますので慣れない方はこちらを利用した方がよいでしょう。筆記用具は、何でも構いませんが、改ざんが容易な鉛筆は不適切です。あるいはワープロ文書をプリントアウトしたものでも構いません。
上記のような形式で、本文、日付、差出人と受取人の住所・氏名(差出人の氏名の下には通常捺印する)を記載すれば、内容証明郵便は出来上がります。なお、文章の内容については、内容証明郵便の書き方に関する書籍が書店に出回っていますのでこちらを参考にするか、あるいは確実を期すためには弁護士に内容証明郵便の作成を依頼するのがよいでしょう。
提出の仕方
内容証明郵便を出すときは、宛名書きした封筒、郵便物の中身である文書のほか、その同一内容の文書2通、すなわち相手方が1人であれば、同じ文書を3通用意して郵便局に持参しなければなりません。郵便局では3通の文書のうち1通を保管し、残りの1通を差出人に返してくれます。また送付する文書は郵便局員の面前で差出人に封筒におさめて封緘させた上で郵便局が受け取りこれを郵送します。その際配達証明付きでと依頼すれば、後日受取人に配達したことを証明する配達証明書がハガキで差出人のもとへ送付されてきます。
料金は、一般の郵便料金の他、書留料金、内容証明料、配達証明料が必要になります。金額は郵送する文書の枚数・重量によって変わりますので、郵便局で確認してください。
補足
このように内容証明郵便は、一般の方でも便利に利用できる郵便ではありますが、文書の内容によっては、充分な法律効果を生じる意思表示となっていなかったり、また自己に不利な内容の事実も書いてしまっていたりする場合もあります。何か不安があれば、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するようにしてください。
また、最近では、インターネット上で内容証明の送付を依頼できるe内容証明もありますので、郵便局のホームページも参照してみて下さい。
離婚手続きの流れについて
離婚手続きの流れ
離婚手続きの詳細については、以前のトピックスで詳しく述べたものがありますので、そちらをご覧下さい。
今回は離婚手続きの流れを、簡単に説明したいと思います。
離婚調停
当事者、つまり夫婦だけでは、離婚の条件等について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の手続きを利用せざるを得なくなるのですが、
離婚は、いきなり訴訟ということが出来ません。調停前置主義といって、離婚等の調停手続きを訴訟より前に行うことになっています。
離婚調停は、これを申し立てる側の配偶者が、相手配偶者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立ててて開始します。
離婚調停においては、調停委員という方々を介して、相手配偶者と話し合う手続きで、相手配偶者と直接話をするのではなく、あくまでも、夫婦双方の希望を調停委員に交互に伝え合う形で話し合いを行う手続きです。
離婚調停の期日において、話し合いをしなければならないのは、主に次のような点です。
①離婚の意思ーそもそも夫婦双方に離婚の意思はあるのか。
夫婦のどちらかの配偶者にそもそも離婚するつもりがないのであれば、調停は不成立になります。
②子どもの親権者、養育費
未成年の子どもがいる場合に、親権者をどちらにするか。
収入が少ない方の配偶者例えば妻が子どもの親権者となる場合、相手配偶者つまり夫は、子どもに支払う養育費の額等詳細を話し合って決定しなければなりません。
③財産分与
夫婦が、二人で築き上げた積極財産はいくらか。不動産や自動車や預金などです。これらを計算して、夫婦で2分の1に分けるのが通常です。
④年金分割
夫婦の一方が相手配偶者の扶養家族となっていた場合に、相手配偶者の厚生年金部分を2分の1に分割して分けるのが通常です。
⑤慰謝料
同居生活中に、夫婦の一方が暴力や不貞行為つまり浮気などの違法行為をした場合に、その違法行為を行った配偶者が相手配偶者に慰謝料を支払うべきだということになります。その慰謝料額を話し合って決定します。
以上のように①~⑤のような論点について、夫婦で、話し合いがつけば離婚調停は成立し、これを調停調書にしてもらうことによって、判決書と同様の効力が発生します。
しかし、いくら話し合っても、夫婦のどちらかが、①~⑤のいずれか、例えば、親権の帰属について話し合いがつかない場合などは、離婚調停は不成立になり、離婚訴訟によらなければ、離婚が成立しなくなることがあります。
その他調停手続きにおいては、あくまでも離婚調停とは別の事件として、
⑥婚姻費用分担の調停
配偶者の一方が、それまでは婚姻費用つまり生活費を支払ってくれていたのに、夫婦別居後に生活費を支払わなくなった等の事情で、生活費を支払ってもらいたい場合、
例えば妻から夫に対して、しかるべく婚姻費用を離婚成立又は別居の解消まで支払ってもらいたいという趣旨の調停が申し立てられたりします。
⑦子どもとの面会交流調停
配偶者の一方が子どもを連れて、夫婦宅を出て行き、その後相手方配偶者が、子どもに会えなくなることがあります。
例えば妻が子どもを連れて夫婦宅から出て行って別居後、夫が子どもに会わせてもらえないような場合です。
このような場合、例えば夫から妻に対して、子どもとの面会交流を認めるように、調停が申し立てられたりします。
⑥⑦いずれも、離婚調停とは別個の手続きですから、離婚調停期日と同じ日に話し合いが行われていても、話し合いがつかなければ、それぞれ審判手続きに移行し、裁判官が審判を下すことになります。
離婚訴訟
前述の離婚調停が不成立となった場合、当事者つまり夫婦のいずれかが、自己の住所を管轄する家庭裁判所又は相手配偶者の住所を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚の判決をもらうためには、裁判上の離婚事由がないと離婚の判決をもらうことは出来ません。
離婚事由というのは、民法第770条に法定されていますが、「配偶者に不貞行為があったとき」や「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」場合を離婚事由として離婚訴訟に至る場合が多いのではないでしょうか?
離婚訴訟にまで発展している場合、夫婦の一方があくまでも婚姻関係の継続を希望している場合は少なく、
むしろ離婚調停で問題になったような、離婚の条件の②~⑤のいずれかで、当事者間に争いがある場合が多いのではないでしょうか?
そのような場合、裁判所は、①~⑤の争点で当事者が判断を求めているものついて審理を進めていくことになります。
審理を進めるにあたっては、裁判所の訴訟指揮により、当事者より、準備書面や書証を出し合って、訴訟が進行していきます。
離婚訴訟に関しては、準備書面や書証のやり取りが必要になってきますので、当事者ご本人で行うのは、大変困難ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
争点が明確になってくれば、当事者夫婦の尋問が行われたりします。
子どもの親権が問題になっている場合には、必要に応じて家事調査官の、調査が行われたりすることもあります。
争点について、当事者尋問等の審理が尽くされた場合は、裁判官は、当事者に和解案を提案して、和解で離婚等を成立させようとしたりします。
それでも、前述の①~⑤の争点で審理対象となっている点について、裁判官の和解案にも当事者のいずれかが納得しない場合は、
前述の①~⑤の争点で審理対象となっている事由について裁判所は判決を下します。
控訴審
家庭裁判所で下された判決について不服がある場合、判決書を受け取ってから2週間以内に判決について不服がある配偶者は、管轄の高等裁判所に控訴することが出来ます。
控訴を受理した高等裁判所は、不服がある配偶者の控訴理由を審理し、もっともな点があればこれを修正した判決を下し、何らのもっともな理由がなければ、控訴を棄却します。
但し、控訴をした配偶者の言い分にもっともな点があれば、高等裁判所は、そのもっともな点を修正した和解案を当事者双方に提示して、和解成立を勧めてくる場合があります。
高等裁判所が勧めてくる和解案に応じるべきかどうかは、ケースによりますので、依頼した弁護士とよく相談して決めた方がよいでしょう。
以上が、離婚手続きの大まかな流れです。最高裁判所への上告については、ほとんど問題になりませんので、省略致します。
調停と訴訟の違いについて
市役所の法律相談などに行くと、よく相談者に調停と訴訟との違いを説明することがあります。そこで、今回は、調停と訴訟との違いを、法律の手続規定はさておいて、大まかな手続の流れに沿って説明してみましょう。
調停手続
まず、調停とは、当事者が話し合いを行う手続であり、特に裁判官が判決のような判断を下したりすることはありません。したがって、調停を申し立てても、相手方が裁判所に出頭しなかったり、出頭しても話し合いがつかなければ、調停は不成立(不調)となります。そうなった場合、調停手続はそれで終了してしまいますから、次は訴訟を起こすなりしなければ事態は進展しないことになります。
調停といっても、離婚や遺産分割等の家事に関することは家庭裁判所に申し立て、貸金や損害賠償等の請求の場合は、簡易裁判所に申し立てなければなりません。申し立てる内容によって管轄する裁判所が違いますので注意を要します。しかし、調停の申立は、申立書の用紙が裁判所に備えおかれており、それに必要事項を書き込むことにより申し立て可能ですから、一般の方でも、特に弁護士に依頼しなくても申し立てることが出来ます。一般の方が自分で申立を行うなら、費用も印紙代や郵券代等で済みますから安くつきます。必要書類なども、裁判所の受付に行けば、たぶん親切に教えてもらうことが出来るでしょう。
例えば、離婚調停を家庭裁判所に申し立てた場合を例にとりましょう。申立を行うと、裁判所が第1回の調停期日を決めて、これを相手方(この場合は他方の配偶者)に通知してくれます。相手方が調停期日に裁判所に出頭すれば話し合いが始まります。この話し合いは、当事者同士が直接行うのではなく、調停委員を仲介役として行います。つまり、当事者双方が、交互に調停室に入り、調停委員にそれぞれ自分の言い分を伝え、調停委員がこれを他方に伝えるという方法による話し合いです。申立人の控え室と相手方の控え室は別々になっていますから、原則として、話し合いを行っていても申立人と相手方が直接顔を合わすということはありません。調停委員は、たいてい年配の男性と女性の2名がその任にあたっています。裁判官が出てくるのは調停が成立するときくらいのものです。調停委員は、時には自分の意見を述べたりして、話し合いが円滑に成立するように努力してくれるわけですが、必ずしも法的知識に基づいて意見を述べているというわけでもない場合が多いので、調停委員の意見は、人生経験豊富な方の貴重な意見としてとらえた方がよいでしょう(もちろん特に専門知識を要するような調停では、その分野に詳しい方が調停委員になっている場合もありますので要注意。)。
このように話し合いが進み、離婚調停であれば、離婚することや、子どもがいればその親権をどちらがとるか、養育費はどうするか、財産分与はどうするか、慰謝料はどうか、子どもとの面会交渉はどうするかなどにつき話し合いがまとまれば、調停成立の運びとなります。調停が成立すれば、合意の内容をまとめた調停調書が作成され、調停調書は判決と同じ効力を持ちます。したがって調停で決めた養育費や慰謝料などを支払ってもらえない場合には、調停調書に基づいて相手方の財産に対し、強制執行をかけることも可能になります。ところが一方、こどもの親権をどちらがとるか等で話し合いがどうしてもつかない場合、調停は成立せず、調停不成立となります。この場合は、前述のように調停手続はそれで終了しますので、申立人としては、その後は離婚訴訟の提起をするなりを検討しなければ、事態は進展することはないでしょう。以上が調停手続の大まかな流れです。
訴訟手続
では、次に訴訟とはどういうものでしょう。少額訴訟というものもありますが、ここでは通常の訴訟手続を念頭に、その大まかな流れを追ってみましょう。
訴訟を提起するには、訴状を作成して管轄裁判所に提出して提起します。訴状には、請求する権利ごとに定まった要件事実(権利が発生するのに必要な事実)等必要事項を記載しなければなりません。例えば、貸金返還請求事件であれば、金を貸し渡したことと支払期限の到来が要件事実です。そして、定められた印紙額や郵券も添えて提出します。
訴状が受け付けられると、裁判所は、第1回の口頭弁論期日を定め、訴状等を相手方すなわち被告に送達します。定められた期日に被告が何の答弁もせず出廷しなければ、原告の言い分を認めたものとして、原告勝訴の判決が下されます。つまりは、訴訟の場合、被告には応訴義務があり、応訴しない場合は敗訴判決という不利益を被るのです。被告が口頭弁論期日において答弁書を提出したり、出廷して応訴した場合、審理が始まります。
口頭弁論期日において、原告が訴状を、被告が答弁書を陳述し、その後の期日においても、双方が準備書面に各自の主張を書いて提出し、基本的に書面によって双方の主張の食い違い、すなわち争点を整理していきます。訴状や答弁書、準備書面の他に、書証(証拠書類)があれば、原被告各自がこれらを提出します(原告が提出する書証は甲号証、被告が提出する書証は原則的に乙号証として提出します)。そしてある程度争点が明確になってくると、裁判所は争点整理を行います。
例えば、貸金返還請求訴訟において、原告が被告に対して500万円を貸したので返せと主張するのに対して、被告が、借りたのは200万円で、300万円は工事代金として受領したものだ、しかも借りた200万円についても、自分のトラックを渡して終わりにしてもらった(代物弁済した)と主張した場合、争点は、大まかには、①原告が貸したのはいくらか、②被告が行ったという工事契約の詳細、③被告がトラックを代物弁済したか、の大きく3点になります。
争点が明らかになれば、原被告は、各自自らの主張を立証するために、人証申請をし、尋問が行われます。ここで、証人や原被告本人に対する尋問が行われ、裁判所は、原被告どちらの言い分が正しいのか、心証を形成します。尋問が行われる前後には、当事者双方において和解の途がないのか模索したりもします。
尋問が終わり、和解の途もないということになれば、裁判所は、口頭弁論を終結し、判決言い渡し日を決めて判決を下します。判決というものは、基本的に、原告の請求を認容する(もちろん一部認容というのもあります)か、あるいは棄却するかの2種類しかありませんので、まさしく白か黒かという判断が下されるわけです。
但し、注意しなければならないのは、裁判官も人間であり、事実を認定し、それを法的に評価し、判決を作成するにあたって、主観的判断を完全に排除することは不可能であるということです。したがって、同じ事件でも裁判官が代われば、違う判決になる場合も往々にしてあるということです。よく、地方裁判所の判決を、高等裁判所が覆すということがあるのも、裁判官によって事件の見方が違うことのあらわれといえるでしょう。このように、判決というものは、勝敗の判断が微妙な事件になればなるほど、それを下してもらうことが一種の賭けのようなものになるのです。ですから、勝敗が微妙な事件においては、オール・オア・ナッシングの判決に賭けるより、何とか当事者双方が納得できる内容の和解を成立させることのほうが無難な場合もあるのです。和解か判決かの判断は、裁判官が原被告どちらを勝たせるつもりか自分の心証を語らず、ポーカーフェイスに徹している場合などには、事案によっては本当に難しいことがあります。
それはさておき不幸にも、敗訴判決を下された被告または原告は、判決に不服であれば、判決書を受領してから2週間以内に上訴(控訴・上告)することが出来ます。原告の勝訴判決が確定すれば(確定しなくても判決に仮執行宣言というものが付されていれば)、その判決に基づいて被告の財産に対し、強制執行が可能になります。
まとめ
少々長くなりましたが、以上が、調停手続と訴訟手続の違いです。調停手続は、一般の方でも簡易に申し立てることができる手続ですが、あくまでも話し合いですので、相手方が出頭しなかったり、話し合いがつかなければ調停不成立です。但し、話し合いがまとまり、調停が成立すれば調停調書は、判決と同一の効力を有します。
訴訟手続は、被告に応訴義務があり、被告が、答弁書も提出せずに出廷しなければ敗訴の不利益を被ります。また訴訟においては、当事者の話し合いがつかなければ判決が下され、原被告のいずれかの勝訴・敗訴が明白にされます。訴訟手続は、一般の方の手に負えないものが多いと思われますので、やはり早めに弁護士に依頼された方がよいと思われます。
借地ー借地契約の更新拒絶の正当事由について
事例
A土地の地主Xさんは、パンの製造業者であり、営業上工場の拡大が不可欠な状態であるが、新規に土地等を取得するほどの資金的余裕がありません。またXさんは、パン工場の拡大を図るならA土地以外にないと考えており、それが営業上もベストな立地条件のようです。
一方借地人のYさんは、10年前からA土地を賃借しており、既製服製造卸売り業者であり、A土地で工場を営んできました。Yさんは、10年間この工場を営んできて、A土地周辺を基盤として得意先を有しており、経営もそこそこうまくいっています。しかしながら、工場が多少手狭になってきたこともあり、近隣に適当な工場用地がありそうな状況なので、工場を移転しようかと時々考えていたところです。
Xさんとしては、多少の立ち退き料を支払ってでも、近く期間満了となるYさんとの借地契約の更新を拒絶し、A土地で自身のパン製造工場を営みたいと考えていますが、かかる更新拒絶に正当事由が認められるか考えてみましょう。
正当事由の内容
XYの借地契約は、10年前からあるようですから、借地借家法ではなく、旧借地法の適用になると思われますが、契約の更新拒絶に正当事由が必要であることに変わりはありません。
この正当事由の内容は、借地借家法によって、より具体的に定められていますので、これが旧借地法適用の場合でも参考になるでしょう。借地借家法では、更新拒絶のためには、
①賃貸人及び賃借人が土地の使用を必要とする事情
②借地に関する従前の経緯
③土地の利用状況
④賃貸人が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引き換えに借地人に対して財産上の給付(いわゆる立ち退き料等)を申し出た場合のその申し出を考慮して、正当事由を判断するものと規定していますので、本件でもこれらの要素を総合的に考慮することになるでしょう。
なお、①~④の判断要素には、主従があり、①が主たる判断要素、②~④は、従たる要素と考えられます。したがって、そもそも①の賃貸人の土地使用の必要性がなければ、その他の②~④の従たる要素を具備しても、正当事由は認められそうにありません。
本件の場合
本件においては、①A土地の使用を必要とする程度においては、Yよりも地主Xの方が勝っているのではないでしょうか。したがって、主たる要素は具備していそうです。②の従前の経緯は、事例ではよく分かりません。③土地の利用状況という点においては、Yは、現にA土地で既製服の製造卸業を営んでおり、A土地周辺を基盤として得意先も持っており、経営もそこそこうまくやっている、ということですから、Xにとっては、あまり有利な要素とはならないでしょう。
そこで問題となってくるのが、④Xが支払っても良いと考えている、立ち退き料の額です。かかる場合の立ち退き料の算定は、さまざま考えられるでしょうかが、少なくともA土地の借地権価格(借地法により保護された借地を使用収益することにより借地人に帰属する経済的利益を表示した金額)やYの営業補償(工場移転によりYが被る営業上の不利益の補償)、工場の移転費用等が問題になることでしょう。
結局Xが、Yに対して、いくらの立ち退き料を提示できるかが、重要な要素となることでしょう。ただ、Xとしては、新たな土地等を取得するほど資金的余裕がないから、A土地の契約更新の拒絶をするわけですから、Yに対して過大な立ち退き料を提供するわけにもいかないことでしょう。またYとしては、近隣に適当な工場用地がありそうな状況なので、工場を移転しようかと時々考えていたというのですから、Xとしては、このあたりも考慮してもらいたいところです。
結論として、本件の場合、XがYに対して相当の立ち退き料の提供を行った場合、契約更新拒絶に正当事由が認められる可能性がある、といったところでしょう(相当の立ち退き料とはいくらなのかは難しい問題です。)。
もっとも、立ち退き料の点で、XとYが合意に至れば、借地契約は合意解除できることはもちろんです。
借家ー敷金返還と原状回復義務について
借家契約が終了する際には、借家人は借家を原状に回復をした上で、家主に返還、すなわち借家を明け渡さなければなりませんし、家主は、借家人から預かっていた敷金等を精算しなければなりません。この原状回復義務と敷金返還について考えてみましょう。契約によっては、敷金ではなく保証金であったり、礼金・権利金を家主に差し入れている場合もありますので、その違いも検討しなければなりません。
敷金
敷金とは、賃貸借契約上の賃借人の未払い賃料や原状回復費用等の債務を担保する趣旨で、賃借人が賃貸人に交付する金員で、賃貸借契約終了の際、これらの賃借人の債務を差し引いても残額がある場合は、当然返還されるべきものです。
権利金
権利金は、その性質が一義的ではありませんが、権利金の性質は、
- 営業上の利益や場所的利益の対価
- 賃料の一部前払い
- 賃借権に譲渡性を付加する対価
- その他
後述の礼金と同じ趣旨のこともあるようです。
権利金は、原則として、賃借人への返還が予定されていない点に特徴があります。但し契約上の賃貸借期間の満了前に契約が終了した場合には、賃借人は権利金を交付したかわりの利益を十分に享受していないと考えられるため、権利金の一部返還が認められる可能性があるでしょう。もっとも、③④の趣旨で交付された権利金が返還されることはないものと考えられます。
礼金
礼金は、一般的な住宅の賃貸借契約において権利金と呼ばれているものと同じです。その金額が低額な場合は、法的には賃貸人への謝礼(贈与)の趣旨か原状回復費用の前払いの趣旨かと思われます。したがって、かかる礼金は賃借人に返還されないでしょう。
保証金
保証金とは、ビルやマンションの賃貸借に際し、賃借人が支払うもので、一定期間据え置き後分割返還するとか、賃貸借契約終了時に一定額を差し引いて返還するとかの特約がなされているのが通常です。
保証金の法的性質についても、一義的には決められませんが、
- 建設協力金
- 貸金
- 敷金
- 期間途中に解約になった場合の空室損害補償
- 権利金等の性質
が混在していると考えられます。
敷金等の自動控除特約
賃貸借建物明け渡しの際、当然に敷金等の何割かを控除しその残額を返還する旨の特約が結ばれることがあります。いわゆる敷引き特約(自動控除特約)と呼ばれるものです。
その趣旨は、家屋の賃貸に伴う通常の損傷に関する原状回復費用に充当するものと考えられますが、具体的には、
①家屋の賃貸に伴う通常の損傷に関する原状回復費用は、本来家主が負担すべきだが、これを借主の負担とする趣旨、
②原状回復費用は契約終了時に具体的に計算し判明するはずだが、敷金等の何割かを差し引くという事前の合意で簡便化をはかる趣旨が考えられます。
判例は、かかる敷引き特約の有効性について、個別のケースごとにその合理性等から判断していますが、一般的には敷引き特約を有効と判断しているものが多く、不合理な特約である場合等にその特約の全部または一部を無効として取り扱っているようです。
原状回復につき特約がない場合の原状回復
前述のように賃借人は、賃貸借契約終了の際には、賃借物を原状に回復した上で賃貸人に返還、すなわち明け渡しを完了しなければならず、その後でなければ、敷金等の返還を受けることが出来ません。原状回復の内容について、契約に特約がない場合を考えてみましょう。
「原状に回復する」とは、賃借人が設置したものを取り除くという趣旨であり、借りた当時の賃借物の状態を復元することとは違います。したがって、通常の使用によって古くなった物の交換をするなどの義務は、本来ありません。
しかしながら、賃借人には、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって賃借物を保管する義務も負っていますから、故意や過失で賃借物を毀損してしまった場合には、毀損部分の損害を賠償する義務があります。
したがって、賃借人が原状回復義務や善管注意義務に違反して損害賠償義務を負っている場合は、敷金等からこれらの賠償額が控除されて残額が返還されることになります。
逆に、賃借物の通常使用に伴う時間的経過による損耗(自然的損耗、たとえば畳、ふすま、障子やじゅうたんの時間的経過による損耗、結露や湿気による壁のクロスの汚損など)については、賃借人は責任を負わないという結論になるでしょう。
ただし、前述のように、契約に敷金等の自動控除特約がなされている場合で、それが有効と認められる場合、自然的損耗の原状回復費用は、敷金等の控除分によって填補されるでしょうから、結局賃借人が負担している結果となりますが・・・。
特約がある場合の原状回復
それでは、たとえば契約書に「賃借人は、契約終了時、畳、ふすま、障子を全部張り替え、壁のクロス、じゅうたんもすべて取り替えを行い、その費用全額を負担する。」など一切の原状回復義務を賃借人に負わせる趣旨の特約があった場合はどうでしょう。
まず、故意過失を問わず、一切の原状回復義務を賃借人に負わせる特約があっても、大修繕に該当する部分(壁のクロスやじゅうたんの取り替えなど)については、これを賃借人の責任とするのは、賃借人に酷なのでかかる特約部分は無効でしょう。
小修繕に該当する部分(畳、ふすま、障子の張り替えなど)の特約部分についてですが、かかる特約が無効とまでは言えないかも知れませんが、特約によって回復すべき汚損、毀損等には、自然的損耗は含まれないという判例もありますから、かかる特約があっても自然的損耗があるにすぎない畳やふすま、障子などを賃借人が全部張り替えなければならない結果にはならないものと思われます。
ただ、かかる特約によって賃借人が負担する原状回復の範囲については、賃料その他の賃借条件等を総合的に検討しなければ、即断は出来ないので注意が必要です。
離婚について
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚
協議離婚は、当事者双方が合意し協議離婚届出書を市区町村長に届け出て、これが受理されることにより成立する離婚です。夫婦間において話し合いが可能で、親権者の指定や、財産分与、慰謝料、養育費の額等が話し合いによって解決できる場合は、協議離婚の方法によることが可能です。
調停離婚
しかしながら離婚やこれに伴う親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費の額等で夫婦間の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立て、話し合いを行うことになります。離婚については、いきなり訴訟を提起することは出来ず、その前に調停の申し立てをしなければならないきまりがあるのです(調停前置主義)。
離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則です。家庭裁判所には調停申立用紙が備え付けられているので一般の人が自分で調停申立をすることも容易になっています。この申立用紙に必要事項を記入し、必要額の収入印紙や郵便切手、戸籍謄本を添付して提出すれば調停申立が出来るようになっています。
調停の進行は、家事審判官1名と調停委員2名の合議体である調停委員会が行います通常は、調停委員2名が夫婦双方の言い分を聞き取り、調整を行い、あとでまとめて家事審判官への報告を行います。調停の期日はおおむね1月に1度程度決められ、夫婦双方が家庭裁判所に出頭して、調停委員にそれぞれの言い分を話し、調停委員が双方の言い分を調整する作業を行っていきます。
経験豊かな調停委員が双方の言い分を聞き、双方が納得できるような譲歩を求める説得を行ってくれるので、当事者だけで話し合いを行うよりも合意が成立する可能性は高いと言えます。しかしながら調停手続きもあくまでも話し合いの手続きですので、当事者の一方がかたくなに自分の主張を変えないような場合(例えば離婚には絶対応じないと主張するような場合)には、調停は不成立となり、終了するしかありません。
当事者双方の話し合いがまとまり、離婚調停が成立するときには、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同様の効力を有し、調停成立によって離婚が成立します。申立人は、調停成立の日から10日以内に、離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村長に離婚届を提出しなければなりません(報告的届出)。
審判離婚
調停が成立しない場合であっても、主要事項については合意にいたっている場合(離婚の合意は出来ているが、財産分与や子の監護の方法等にわずかな相違があるために調停にいたらないような場合)や、当事者の一方が遠隔地にいるために調停期日に出頭できないが離婚の意思は有している場合等に、改めて離婚訴訟を提起させるのは、申立当事者にとっても社会経済的にも無駄であることから、家庭裁判所が職権で調停に代わる審判を行うことがあります。
ただし、調停に代わる審判は、審判の日から2週間以内に審判内容に不満がある当事者から異議申立があると効力を失ってしまうので、審判を行うことが出来るケースは自ずと限られてくることになります。
裁判離婚
前述のように離婚訴訟を提起するためには、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりませんが(調停前置主義)、夫婦双方の話し合いがつかず、調停不成立となり調停に代わる審判もなかったような場合には、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟は、
①夫婦が共通の住所を有するときは、その住所を管轄する家庭裁判所、
②夫婦の最後の共通の住所地を管轄する家庭裁判所区域内に夫又は妻が住所を有するときには、その住所地を管轄する家庭裁判所、
③夫婦が上記管轄区域内に住所を有しないとき及び夫婦が共通の住所地を有したことがないときは、どちらか一方の普通裁判籍の所在地の普通裁判籍所在地を管轄する家庭裁判所等に訴状を提出して提起します。
訴状においては離婚の請求だけでなく、財産分与、慰謝料、養育費の請求、親権者の指定も求めることが出来ます。しかし離婚訴訟を提起するとということになれば、通常当事者本人が行うことは困難ですので弁護士に依頼した方がよいでしょう。
離婚事由
離婚訴訟を提起できる場合は、次の場合に限られていて、かかる離婚事由が認められなければ、離婚等の請求は棄却されることになります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
また、裁判所は、①~④の離婚事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することも出来ます。
上記の離婚事由は、それぞれ次のような意味です。
(1)不貞行為=配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。いわゆる浮気はこの不貞行為に該当します。
(2)悪意の遺棄=正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。
(3)3年以上の生死不明=3年以上も生存も死亡も確認できない状態が現在も引き続いていることを言います。
(4)強度の精神病=その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務、ことに他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を充分に果たし得ない程度に達している場合を言います。
(5)婚姻を継続しがたい重大な事由=婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味します。しかし、具体的にどのような事情をもってこれを認定するかは、裁判官の自由裁量に委ねられており、このことから抽象的離婚原因と呼ばれています。
(5)に該当する可能性のある事由としては、暴行・虐待、重大な病気・障害、配偶者の過度の宗教活動、勤労意欲の欠如、性交不能、親族との不和、性格の不一致などが考えられます。
上記の離婚事由が認められる場合、裁判所は離婚等の請求を認容する判決を下します。財産分与、慰謝料、養育費の請求、親権者の指定も求めていれば、これらの請求に対する判決も下されます。離婚請求認容判決が確定すると婚姻は将来に向かって解消することになります。そして、離婚請求認容判決が確定すると、その日から10日以内に、判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村長に対し離婚届を提出しなければなりません(報告的届出)。
また、離婚訴訟においても通常訴訟と同様に和解により終結することがあります。しかしこの場合、離婚の届出は協議離婚として届け出ることになります。
有責配偶者からの離婚請求
最高裁判所大法廷昭和62年9月2日判決は、一定の要件のもとで有責配偶者(婚姻関係の破綻について責任がある配偶者、例えば愛人を作って自宅を出て、妻のもとに長年帰らなかった夫など)の離婚請求も許される場合がある旨判示しました。
すなわち、この判決は、「①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって(離婚請求が)許されないとすることはできない」と判示したのです。
最近の過払い金返還請求の状況
最近のサラ金等金融機関に対する過払い金返還請求の状況は、端的に言うと以前より時間や手間がかかるようになっています。
というのも、サラ金等金融機関は、過払い金の返還額について、まずもって交渉段階では利息を付しませんし、取引期間に空白期間があると、それぞれの取引が別取引だと主張し、10年以上経っている取引を見つけると、過払い金返還請求権が消滅時効にかかっていると主張すること等法的な主張を当然にしてきます。
さらには、自社の経営的苦境を訴え、過払い金元本額の5割程度の返還やひどい金融機関になると過払い金元本の5%程度の返還で勘弁して欲しいなどと懇願してきたりします。
返還期限においても、やはり自社の予算の都合を訴え、半年以上後の返還期限を提案してきたり、ひどい金融機関になると、長期の分割弁済を提案してきたりします。
サラ金等金融機関の担当者が有する裁量権はあまり広く認められていないようで、ある程度の返還額増額や返還期限の早期化の譲歩はするものの、それ以上は、担当者レベルではどうしようもないという返還金額や返還期限が提案されます。
かかる金融機関の提案する過払い返還金額や返還期限に応じることが出来なければ、もはや交渉から訴訟提起に方針を切り替え、やむを得ず不当利得返還請求訴訟を提起する場合があります。
訴訟ということになれば、原告側としては基本的に過払い金額全額及びこれに対する年5%の利息を請求していくことになります。
しかし、場合によっては、判決によっても年5%の利息が認められないこともありますので、早期に過払い金元本全額に近い金額が回収できるのであれば、訴訟手続中においても訴訟外または訴訟上において、サラ金等金融機関と和解することもあります。
結局のところ、交渉段階で和解できたとしても、訴訟提起後和解、判決に至ったとしても、現実に金員の返還が実現するまでには、過払い金返還請求の受任をしてから5ヶ月から半年程度の時間を要する場合が多くなったという状況です。
もっとも上記は一般論であり、金融機関によっては、もっと好条件で解決できたり、もっと悪条件の結果しか実現できない場合もあります。